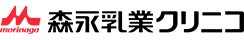がん治療中の低栄養とは
がんと低栄養の関係

がん患者の低栄養、体重減少は通常よく見られるものです。とくに消化器がん、肺がん、頭頸部がんでは半数以上と高頻度で認められます1)。加えて、治療を受ける時点ですでに栄養障害に陥っていたり、治療中・治療後にもがん自体の影響や治療の副作用などで栄養障害に陥ったりすることが多いとされています2)。
体重減少が見られるがん患者は、体重が維持されていたがん患者に比べ、治療の副作用が発生しやすくなる、薬物療法の効果が低下する、活動性が低下する、QOL(生活の質)が低下する、といったことが報告されています2)。
がんに対しては、3大療法と総称される、手術、放射線治療、薬物療法が主に行われます。
どの治療を行うにあたっても栄養サポートは非常に重要です。
手術では、術後、長期にわたって栄養状態が変化する可能性があるため、定期的に栄養状態を評価し、必要に応じて流動食や栄養補助食品の使用を検討することが望まれます3)。
放射線治療では、治療の中断を避けるために、栄養カウンセリングや栄養補助食品などの使用によって十分な栄養を摂取することが推奨されています。
薬物療法では、適切な栄養摂取量の維持が推奨され、副作用の影響で経口での摂取量が不十分な場合は経腸栄養や静脈栄養も推奨されます4)。
「がん関連性低栄養」と「がん誘発性低栄養」
がん患者の低栄養は、治療に伴って生じる「がん関連性低栄養」と、がん特有の病態によって生じる「がん誘発性低栄養」に分けられます。2つが相乗的に作用することで、予後に大きな影響を及ぼすと考えられています2)。


がん関連性低栄養は、手術や放射線治療、薬物療法の副作用などによって、栄養摂取量が低下することで生じます。具体的には、食欲の低下や、疼痛、口内の炎症・乾燥などによる経口摂取量の低下、消化管の機能の低下や下痢などによる消化吸収能の低下が挙げられます。また、増大したがんの病巣そのものや、がんに伴って生じた腹水などの影響で消化管を食べ物が通りにくくなることも原因となります1)。
がん誘発性低栄養は、がん特有の病態によって生じ、単なる栄養補給では解消できない低栄養に陥っていることをいいます。代表的な病態が「がん悪液質」と呼ばれるもので、通常の栄養サポートでは完全に回復することができずに進行性の機能障害に至る、骨格筋量の持続的な減少を特徴とします5)。がん悪液質のメカニズムは完全には解明されていませんが、がんが体内に存在することによって生じる炎症反応が代謝異常や食欲不振、骨格筋減少などにかかわっていると考えられています6)。

-
1)濱口哲也, 三木誓雄: がん患者の代謝と栄養. 日本静脈経腸栄養学会雑誌. 2015; 30(4):911-916.
-
2)日本静脈経腸栄養学会(現:日本栄養治療学会)「静脈経腸栄養ガイドライン 第3版」
-
3)Bozzetti F, et al. Postoperative complications in gastrointestinal cancer patients: the joint role of the nutritional status and the nutritional support. Clin Nutr. 2007 Dec;26(6):698-709.
-
4)Arends J, et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2017 Feb;36(1):11-48.
-
5)Fearon K, et al. Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. Lancet Oncol. 2011 May;12(5):489-95.
-
6)日本がんサポーティブケア学会 「がん悪液質ハンドブック」
医療・介護従事者の方向けに、がん栄養療法関連ガイドブックをご用意しています。