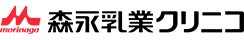経腸栄養の下痢と
対処方法について
頻度の高い消化器系合併症

経腸栄養において、とくに多い合併症として挙げられるのが下痢で、経腸栄養を受けている患者の20~72%で生じると報告されています1)。脱水や電解質異常を高頻度で引き起こすという報告2)もあり、注意が必要でしょう。
下痢は、流動食を原因として生じる場合と、流動食とは別の原因で生じる場合があります。それぞれについて見ていきましょう。
流動食に関連する下痢への対処
流動食に関連する下痢は、摂取速度に原因がある場合と、流動食自体に原因がある場合が主に挙げられます。
摂取速度は速すぎると腸のぜん動が活発になり、腸管での消化吸収が追いつかなくなってしまいます。そうならないよう、初日はゆっくりとした速度で摂取し、1~3日後に速度を上げるなど、様子を見ながら徐々に速度を上げていくのが望ましいでしょう。もし、患者さんが腹部膨満、腹痛、下痢などを訴えたら、速度を落として経過観察を行います3)。
流動食に含まれる乳糖や脂肪、食物繊維、難消化性の糖質などが下痢の原因となる場合があります。その場合、該当する栄養素が少ないものに変更します。また、流動食や器具の細菌汚染が原因となる場合もあるため、適切な管理で防ぐことも大切です。
流動食に関連しない下痢への対処
流動食に関連しない下痢は、患者さん自身の病態に関連する場合と、薬剤に関連する場合が主に挙げられます。
患者さん自身の病態としては、ストレスなどによって消化管の運動異常を引き起こす過敏性腸症候群(IBS)などが挙げられます。その際は薬物治療や、流動食の使用によって改善を目指します。
下痢を引き起こす可能性がある薬剤としては、低下している消化管の運動を促す消化管運動賦活剤や、血糖の上昇を抑えるα-グルコシダーゼ阻害薬、胃酸分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬が挙げられます。こうした薬剤が原因と考えられる場合は可能な限り使用を中止します。
また、抗生剤の長期使用も下痢の原因となる可能性があります。抗生剤の長期使用によって、腸内細菌叢のバランスが崩れる場合があります。それ自体が下痢の原因となるほか、バランスが崩れることで、下痢を引き起こすクロストリジオイデス・ディフィシル(Clostridioides difficile)という細菌が異常に増殖することもあります4)。このクロストリジオイデス・ディフィシル感染症(CDI)が疑われる場合は、原因と思われる抗生剤の使用を中止して、症状への治療を行います。


-
1)日本静脈経腸栄養学会(現:日本栄養治療学会)「静脈経腸栄養ガイドライン 第3版」
-
2)陣場貴之ほか: 当院 NSTが介入した下痢症例に関する検討~電解質異常に着目して~. 日本静脈経腸栄養学会雑誌. 2015; 30(6): 1296-1299.
-
3)宮澤靖: 経腸栄養. 静脈経腸栄養. 2007; 22(4): 455-463.
-
4)安藤朗, 馬場重樹:Ⅲ.Clostridium difficile感染症の現状. 日本大腸肛門病学会雑誌. 2018; 71(10): 456-469.
医療・介護従事者の方向けに、栄養関連情報や学術情報などを公開しています。