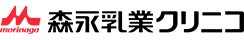流動食の選択方法は?
消化吸収能の確認
流動食を選ぶ際は、腸管機能や患者さんの病態など、さまざまな要因を確認していきます。
まず確認するのが腸管機能(消化吸収能)です。
腸管は絶食などで使われないままだと、粘膜が萎縮してバリア機能が低下するといわれています1)。そうした状態を防ぐためにも、腸管が機能していれば腸管を使うことが原則です。
腸管が十分に機能していれば、消化を経て吸収される「半消化態流動食」を選択できます。機能が低下している場合には、消化が容易な「消化態流動食」や、「成分栄養剤」が選択されます。

病態の確認
次に確認するのが、患者さんの病態です。
病態によっては、たんぱく質や炭水化物、脂質など、各栄養素の含有量・バランス・質などを調整したり、特徴的な栄養成分を添加している製品を用いることがあります2)。たとえば、電解質やたんぱく質などの摂取量を調整する必要がある腎疾患や、糖質の量を調整する必要がある糖尿病などが挙げられます1)。
摂取量や水分量の考慮
腎疾患や糖尿病など、特定の病態に配慮した流動食を選択する必要がない場合には、摂取量や水分量を考慮して濃度を検討していきます。
水分量は一般的に体重1kgあたり30~40ml/日と算出されています1)。必要な水分がしっかり摂れていなければ追加水を投与しますが、その手間を省くことができ、より衛生的な低濃度タイプも選択できます。また、1回あたりの摂取量や水分量を抑えたい方に対しては高濃度タイプを選択できます。
なお、標準組成の流動食に区分されるものでも、たんぱく質やナトリウム、ビタミン、食物繊維などの配合量・質にこだわった製品が各メーカーから販売されています。
たとえば、必要なたんぱく質、ビタミン、微量元素などを1日800kcalの摂取でも補える製品や、腸内細菌叢の正常化や便性改善などを期待して食物繊維やオリゴ糖、乳酸菌が配合された製品が挙げられます。
また、消費者庁の許可を得た上で、病者などの健康の保持・回復などに適することが表示できる、特別用途食品「総合栄養食品(病者用)」の製品もあります。

-
1)日本静脈経腸栄養学会(現:日本栄養治療学会)「静脈経腸栄養ガイドライン 第3版」
-
2)佐々木雅也:経腸栄養剤の種類と特徴~病態別経腸栄養剤の種類と特徴~. 静脈経腸栄養. 2012; 27(2): 637-642.
-
3)消費者庁ウェブサイト「特別用途食品について」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses/
医療・介護従事者の方向けに、使用事例などの学術情報をご用意しています。