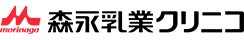病態別流動食の
活用方法は?
監修:
医療法人社団 悦伝会目白第二病院 副院長 水野 英彰 先生
一部の病態にあわせた流動食
流動食の中には、特定の病態に応じて各栄養素の含有量・バランス・質などを調整したり、特徴的な栄養成分を添加したりしている製品があります。それらを適切に選択することで、栄養補給に加えて、おおもとの疾患の治療に役立てることも期待できます1)。
病態別流動食

| 肝疾患 | 肝不全患者では、筋肉のエネルギー源となる分岐鎖アミノ酸(BCAA)の血中濃度が低下します2)。それを補えるよう、BCAAを豊富に含有した上で、たんぱく質、ビタミン、微量元素などが肝不全患者の病態を考慮して配合された流動食が用いられます。 |
|---|---|
| 腎疾患 | 腎疾患患者では、体内の老廃物や水分の排出、血液中の電解質のバランスを保つといった腎臓の機能が正しく働かなくなります。そのため、水分や塩分、リン、カリウムなどが調整された流動食が用いられます。 |
| 耐糖能異常・糖尿病 | 耐糖能異常や糖尿病の患者では、食後の血糖値の上昇がみられます。そのため、糖質の割合を少なくした流動食や、糖質の吸収に配慮した難消化性デキストリン配合の流動食が用いられます。 |
| 呼吸器不全 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器不全患者は、酸素を取り込む機能や二酸化炭素を排出する機能が低下しています。そのため、二酸化炭素の発生量が炭水化物に比べて少ない脂質を増やした流動食が用いられます。 |
周術期
周術期では術後、消化吸収機能が低下している場合、空腸から経腸栄養を行う場合などにおいて消化態流動食を選択することがあります。その際は、48時間以内に使用を開始するのが望ましいでしょう。また、長時間の絶食後に経腸栄養を行う場合にも消化態流動食を選択することが多いようです。


-
1)日本静脈経腸栄養学会(現:日本栄養治療学会)「静脈経腸栄養ガイドライン 第3版」
-
2)谷口靖樹, 東口髙志: 慢性肝障害例における栄養管理. 静脈経腸栄養. 2005; 20(4): 4_3-4_9.
医療・介護従事者の方向けに、病態別栄養関連のガイドブックをご用意しています。