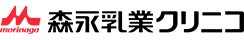製品開発秘話②
つるりんこシュワシュワ編

飲み込みにくいと感じる方にも、安心して炭酸飲料を楽しんでほしい。製品開発グループ・渡辺達也のそんな想いから生まれたのが、とろみ調整食品「つるりんこシュワシュワ」です。
開発プロジェクトが立ち上がったのは、2020年。安全性を最優先しつつ、飲み込みが難しい方でも手軽に炭酸飲料を楽しんでいただくためには、どうすればいいのか。
挑戦の日々が始まりました。
「炭酸飲料を飲みたい」その想いに応えたい

開発プロジェクトの発足は、以前から当社の取り組みについてご指導いただいていた、前田圭介先生(老年内科 医師)からの患者さんを想うご意見がきっかけでした。
「嚥下機能が低下した患者さんの中には、炭酸飲料を飲みたいという方もいる。
しかし、従来のとろみ調整の方法では、炭酸飲料のシュワシュワ感が抜け、それっぽい甘い飲み物になってしまっている。
どうにかして、そういった患者さんに本物の炭酸飲料を飲む楽しみを届けることはできないか。」というものでした。
実はNR(※)として、医療・介護従事者の方に栄養や製品の情報を提供する活動をしていた際にも同じようなご相談を受けることはあり、既存のとろみ調整食品を使用して少しでも炭酸感を残しつつとろみをつける方法をご提案していました。
具体的には、少量の炭酸飲料に濃い目のとろみをつけ、同じ飲料を加えながらやさしくかき混ぜるという方法です。しかしその方法でも、炭酸飲料本来の味わいからはかけ離れ、また、均一なとろみに調整することが難しいという課題もありました。
困難を極めた「ペットボトルでの調整方法」の検討

そうした経緯を経て、開発プロジェクトとしてまず取り組んだのが、既存製品を使って炭酸感を保ちつつ、ダマやムラのない均一なとろみをつけるための調整方法を見出すことでした。
前田先生からのアドバイスを受け、炭酸が抜けないようにするためには、コップではなく密閉容器、つまり炭酸飲料が入っているペットボトルの中でとろみを調整する必要があるということを考えました。
ただ、粉末を入れてからすぐにキャップを閉めて攪拌しなければダマができてしまう可能性があること、そしてペットボトル内のヘッドスペース(液面からキャップまでの空間)がわずかであるため、均一に混ぜることが難しいという課題がありました。
製品の種類と様々な振り方の掛け合わせを試しながら、毎日いたるところで振り続けました。そうしてたどり着いたのがつるりんこPowerfulを用いて、「混合」→「溶解」→「脱気」という3つの工程の攪拌方法を経たあと、冷蔵庫で一晩冷やすという調整方法です。
この方法により、炭酸飲料本来のシュワシュワ感や味わいを残しつつ、均一なとろみをつけることが可能となりました。プロジェクトが立ち上がってから、ここまでに約1年が経過していました。
この方法を動画で配信し、紙媒体の資料として医療・介護従事者に配布したところ、大きな反響があり、改めてこの取り組みの意義を実感しました。「これで患者さんの希望を叶えられる」という喜びの声があった一方で、「やり方が難しい」「動画を見ても失敗してしまった」という声がありました。
日々、忙しい医療・介護の現場で普及させるためには、複雑な調整工程や準備に時間を要する点を改善する必要性を感じました。
トップランナーとしての威信をかけた「炭酸飲料向けとろみ調整食品」の開発
そこで、森永乳業の研究所のスタッフも加わり、炭酸飲料に特化したとろみ調整食品の開発に踏み出しました。
目指したのは、既存製品では実現することができなかった手軽さと、炭酸飲料本来の味わいを安心して楽しんでいただくための製品です。
20年以上にわたり培ってきたとろみ調整食品の製造ノウハウを活かして、ペットボトル内で調整することを前提に、様々な炭酸飲料に対応できる製品設計を検討することから始まりました。
また、これまでにないコンセプトの製品であることから試作品でのモニター調査を実施。とろみ調整食品に馴染みのない方でも、ダマを作りにくく、安心してご使用いただける調整方法を追求していきました。
そうした試行錯誤を経て、2022年9月に満を持して「つるりんこシュワシュワ」を発売しました。350~500mlのペットボトル入りの炭酸飲料に対して、本品1本(2.5g)を加えて30秒程度、素早く強く振り続け、3時間程度冷却することで調整できます。
これまでの方法と比較すると、調整に要する労力や時間を格段に抑えることができ、肝心な風味や炭酸感も想像を遥かに超えるものに仕上がりました。
安心してご使用いただくために

振り返ると開発の過程で数多くの失敗と気づきがありました。
例えば、ノンアルコールビールなど缶入りの炭酸飲料にとろみをつけたい場合、密閉性と耐圧性のある容器に一度移し替える必要があります。
当時、炭酸飲料の扱いに慣れていなかったこともあり、身近にあったプラスチック容器での調整を試みたところ、容器が破裂し全身がとろみつきのノンアルコールビールまみれになりました。
幸いけがはありませんでしたが、製品を届けることと同時に安全にご使用いただくことの必要性を強く認識することができました。
また、先述のモニター調査でも、多くの方々は炭酸飲料を振るという行為に対して無意識に抵抗感を抱いていることに気づきました。
誤えんや窒息への配慮からダマを作らないためにはできるだけ強く振っていただく必要がありますが、多くの方々が遠慮気味に振っていたのです。
この経験から使用方法を正確に伝え、誰しもが安心してご使用いただけるように詳細な解説動画(動画はコチラから)を作成しました。
新たな挑戦であるがゆえに、こうした安全面への配慮を強く意識して進めました。
「こんな商品を待っていた」喜びの声が届く

販売を開始したところ、医療・介護の現場の方からは、「こんな商品を待っていた」という声が多く寄せられ、予想以上の反響がありました。
病院や施設では、クリスマス会やお祝い事など、イベントで使っていただくことが多いようです。実際にご高齢の方から医療的ケアを受けているお子さままで、多くの方々がこの製品を通じて喜んでいただけたという話やご家族で楽しんでいただけたという話を伺い、まさにこれまでの苦労が報われた想いでした。
加齢や疾患によって生活が制限されている方にとって、食事はかけがえのない楽しみのひとつです。
大好きな炭酸飲料を飲みたい、飲み続けたいという想いに寄り添うことができたと実感しています。
TO THE NEXT
炭酸飲料は、嗜好性だけでなく機能性の側面でも注目されています。
具体的には、嚥下機能に対する炭酸刺激がもたらす効果に関して、基礎研究が積み重ねられており、近年では嚥下障害患者へのとろみつき炭酸飲料での臨床研究も進められています。
一部では有効性が示唆される結果も見られており、今後更なる研究が期待されます。
おいしさと楽しさに加えて嚥下の訓練にも役に立てるということになれば、とろみ調整食品を扱うメーカーとして大変喜ばしいことです。
また、商品名の「シュワシュワ」には、いつまでも炭酸飲料を楽しんでほしい、親しみを感じ多くの方々に手に取ってほしい、という私たちの想いが込められています。
飲み込む機能が低下した方も、そうでない方も、一緒に食卓を囲んで乾杯や食事を楽しんでもらいたい。
そんな想いを胸に、これからも一生懸命取り組んでいきたいと思います。

-
※森永乳業クリニコの営業担当者は、NR(Nutritional Representative/栄養情報アドバイザー)という当社独自の呼称で活動しています。臨床現場のニーズを踏まえ、適切な情報提供を心がけています。