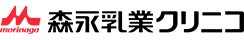vol.9 在宅での経腸栄養管理のポイント


北美原クリニック

サルコペニア・低栄養研究センター センター長
患者さんにあった方法でのお食事・栄養補給

口から食べることは、幸福感につながり、また様々な機能を活性化させてくれます。一方で、口から食べることが難しくなった際でも 様々な方法で栄養を補給し、在宅生活をすごしていくことが可能です。今回は、経腸栄養(胃ろう)での栄養摂取をご紹介します。
1.経腸栄養(胃ろう)管理

医療介護施設での経腸栄養(胃ろう)は専門スタッフが対応していましたが、ご自宅ではご本人やご家族が専門スタッフと連携して取り組むことが大切です。
2.経腸栄養剤(流動食)の種類
経腸栄養剤には形態だけでも液体・半固形・とろみ付など様々な種類があります。どの種類が適しているかは、状態や環境に合わせて専門スタッフからのアドバイスを受けることができます。

3.在宅での経腸栄養(胃ろう)の注意点
経腸栄養の生活では、時にはトラブルが発生することがあります。どのような可能性があるかを、把握しておきましょう。
※気になったトラブルや症状は適切な対応が取れるようにサポートスタッフに相談してください。


胃ろうも「食事」の一つです。流動食によってはフレーバーがついており、げっぷなどにより、香りを感じることができると言われています。安心した食事が摂れる環境をととのえていきましょう。


北美原クリニック
おかえりなさい。在宅医からのエール
退院の時に、経腸栄養管理の方法やトラブルの対処法を聞かれたかと思います。もし退院されて実際に管理するようになって不安や戸惑いがあれば、医師や訪問看護師に遠慮なく聞いてください。今では栄養剤も胃ろうのキットもいろいろなものがあります。患者さんや介護者が管理しやすい方法に変更することで負担が少なくなったり、トラブルを起こさないようになります。
我々もそうですが、経腸栄養を行っていると便秘になったり下痢したりすることがあります。便秘が続く場合には緩下剤を使います。また下痢の場合には整腸剤を使用したり、一時的に栄養剤をストップすることもあります。どちらもひどくなる前に医療者に相談することが大切です。
栄養剤の変更で便秘や下痢が良くなることもあります。適切な経腸栄養を行っていると、退院してきたときに比べてとても元気になられて良く話すようになったり、リハビリをどんどんやれるようになる方がおられます。栄養はすべての基本です。経腸栄養に伴うトラブルや負担をできるだけ少なくできるよう我々がお手伝いいたしますので、一緒に話し合っていきましょう。